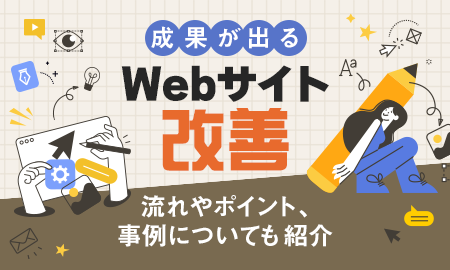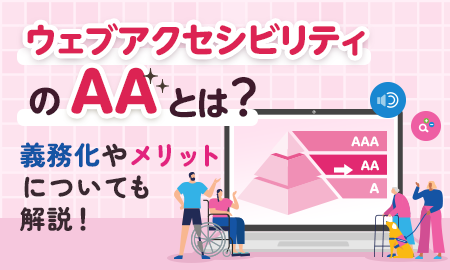サイトリニューアル時のリダイレクト完全ガイド。設定の流れやSEO効果についても解説

サイトリニューアルでURLが変更になった場合は、新しいページへの「リダイレクト」が必要です。リダイレクトとは旧ページから新ページへユーザーを転送することで、正しくリダイレクトが行われているかはSEOにも影響してきます。
本記事では、サイトリニューアルのリダイレクトについて詳しく解説します。初めての方でもリダイレクトを正しく行えるよう、設定の流れやSEOへの影響、設定時の注意点なども記載していますので、ぜひ最後までご覧ください。
サイトリニューアルで検索順位を下げないために必要な「SEOの基礎知識」をまとめた資料がございます。
SEOを考慮したリニューアルを行い集客に強いサイトにしたい方は、まずはこちらの資料を参考にしてみて下さい。
▼訪問者数を増やすために必要なSEO対策の基礎
目次
サイトリニューアル時のリダイレクトとは
リダイレクトとは、旧ページから新ページに転送することです。
サイトリニューアルの際、場合によってはURLを変更することもあると思います。リダイレクト設定をすると、変更前のURLにユーザーがアクセスした場合、自動的に変更後のURLに転送します。
サイトリニューアルでURLが変更となった場合はもちろんですが、サイトメンテナンスなどで一時的に別ページへの転送を必要とする場合や、パソコン用とスマートフォン用のサイトでURLが違う場合も利用されます。
リダイレクトには「サーバーサイドリダイレクト」と「クライアントサイドリダイレクト」があります。サーバーサイドリダイレクトはサーバー側が指示して行うリダイレクトで、ユーザーの行動なしに自動的に新しいURLに転送されます。
一方のクライアントサイドリダイレクトはブラウザ上で行うリダイレクトで、新しいURLに遷移する旨のメッセージが表示されることが一般的です。基本的には、サーバーサイドリダイレクトが推奨されています。
リダイレクトが必要な理由

URLが変更となるサイトリニューアルにおいて、リダイレクトは非常に重要です。リダイレクトを行うことによって信頼性やSEO効果の維持、アクセス減少の防止などが期待できます。ここではリダイレクトの必要性について解説します。
サイトの信頼性を下げないため
リダイレクトはサイトの信頼性を維持するために必要です。
サイトリニューアルでURLが変更になると、旧URLにアクセスしたユーザーには404エラーが返されます。
404エラーを見たユーザーがサイトを利用したいと考えた場合は、検索して移転したサイトを探す手間が生じます。場合によっては移転を知らず「サイトがなくなった」「営業を辞めた」と勘違いするかもしれません。
こうした手間や不満が募れば、ユーザーはサイトを離れてしまうでしょう。満足なユーザー体験ができず、信頼性が低下し、利用を辞めたり他社に流れたりする可能性もあります。
リダイレクト設定を行えば、ユーザーは以前と変わらずサイトを利用できます。信頼性維持のために、ユーザーが快適に閲覧できる環境を整えておきましょう。
SEO効果を低下させないため
リダイレクトはSEO効果を低下させないためにも重要です。なぜならリダイレクト設定をしないと、SEO効果を引き継げなくなり、検索順位が大きく下がる可能性があるためです。
GoogleはサイトリニューアルでURLが変更となったサイトを、新しいサイトと見なします。再度サイトがインデックスされるの待たなければならないうえ、これまで積み上げてきたSEOの効果がリセットされ、検索順位が大幅に低下します。同じ順位まで回復させるには、再び時間をかけてGoogleの評価を取り戻す必要があります。
SEO効果を元に戻すにはスピーディなインデックスが必要ですが、基本的にリダイレクト設定をしないとインデックスも遅くなるとされています。なぜなら、大量のクロールエラーが起こるためです。
リダイレクト設定をするまでは旧URLにクローラーがクローリングに訪れますが、移転後のURLにはサイトがありません。そのため、クローラーがサイトを発見できず、大量のクロールエラーが発生し、インデックスに時間がかかってしまうのです。
アクセスの減少を防ぐため
リダイレクトは、アクセスの減少を防ぐ効果も期待できます。
先述したように、サイトリニューアルでリダイレクトを行わないと、SEO効果がリセットされます。SEO効果がリセットされたり、クロールエラーでインデックスが遅くなったりすると、評価が回復するまで上位に表示されません。それに伴ってアクセス数が減少する可能性があり、大きな機会損失となるでしょう。
リダイレクト設定をすることでSEOの評価が引き継がれ、機会損失が最小限に抑えられます。サイトリニューアル時のアクセス減少の原因は、リダイレクト漏れが特に多いため、確実にリダイレクトを行いましょう。
リダイレクトが必要なタイミング

サイトリニューアル時は変更点が多く発生し、リダイレクトが必要なケースがあります。特にドメインやURLの変更、SSL化の際はリダイレクトが必要です。ここではリダイレクトが必要なタイミングをご紹介します。
webサイトのドメインが変わったとき
サイトリニューアルによってドメインが変更になった場合は、リダイレクトを行いましょう。
サイトリニューアルでは「社名やブランド面が変更になった」「独自ドメインを自社で新しく取得した」などの理由でドメインを変更する場合があります。ドメインが変更になるとURLも変わるため、旧URLにアクセスしたユーザーはページを閲覧できません。こうした事態を防ぐために、リダイレクトが必要です。
なお、サイト移転の方法としてGoogleは「小規模から中規模のサイトは一度に、大規模のサイトは区分ごとに分けて移転」を推奨しています。小規模から中規模のサイトは、一度に移転することによりサイトの検出とインデックスが速くなります。大規模サイトの場合は、区分ごとに移転すると監視や検出がしやすく、問題を解決しやすいとしています。
ページのURLが変わったとき
ページのURLが変更になった場合も、リダイレクトを設定しましょう。先述したドメインによるURLの変更はもちろん、ディレクトリ構造を変える場合などもURLが変更になります。
URLが変更になった場合は、URLの新旧対応表を作成することをおすすめします。リダイレクトで重要なことが「抜け漏れがないこと」です。正しくリダイレクトができておらず、エラーが返ってきたり、全く内容の違うページに転送されたりしたら、ユーザーは混乱してサイトの信頼性が下がってしまいます。
新旧対応表を作成して、抜け漏れがなく正しくリダイレクトされているか確認しましょう。
常時SSL化(https化)対応をするとき
常時SSL化対応を行う際も、リダイレクトが必要です。SSL化とはSecure Sockets Layerの略で、データを暗号化してやり取りする仕組みです。常時SSL化すると、URLの最初がhttpからhttpsに変更となります。この場合、httpからhttpsにリダイレクトが必要です。
常時SSL化のように、同じコンテンツに複数のURLからアクセスできる場合、1つのURLにまとめることを「URLの正規化」と言います。特に多いケースが「index.htmlの有無」「wwwの有無」「パラメータ(ユーザー行動把握などのためにURLにつく変数)の有無」などです。
URLの正規化は、SEO対策として重要です。別のURLで同じコンテンツがある場合、クローラーはそれらを別のページと見なします。別ページだと判断されると、評価が分散する、コピーコンテンツだと誤認される、クロールに時間がかかるといったデメリットがあります。そのため、URLを正規化して、評価を集約させる必要があります。
リダイレクトの種類

リダイレクトには複数の種類があります。サイトリニューアルで主に利用されるのは「301リダイレクト」と「302リダイレクト」です。ここでは301リダイレクトと302リダイレクトについて、詳しくご説明します。
永続的な転送 301リダイレクト
301リダイレクトは、永続的な転送を行うリダイレクトです。一度設定を行えば、旧ページから新ページへ恒久的に転送されます。
ドメインやURLの変更、常時SSL化やURLの正規化など、旧ページに戻らない場合に使用されます。Googleもリダイレクトを元に戻す予定がない場合や、ページのURLを変更する場合は、301リダイレクトの設定を推奨しています。
301リダイレクトと似たものに「308リダイレクト」があります。308リダイレクトも永続的な転送を行う点では、301リダイレクトと同じです。ただ、308リダイレクトはHTTPメソッドを変更せずにリダイレクトができます。たとえば、ショッピングカートの中身をそのままにしておく、天気アプリの地域情報を引き継ぐといったことが可能です。
一時的な転送 302リダイレクト
302リダイレクトは、一時的な転送をするリダイレクトです。何らかの事情で一時的にページが利用できない場合には、302リダイレクトを設定すると良いでしょう。
よくあるケースは、サイトのメンテナンスやテスト、キャンペーンなどで一時的に違うページを表示したい場合です。メンテナンスの場合は「お知らせ」ページに転送して、メンテナンス中であることを知らせることも多いです。基本的には、元のページに戻る場合に利用されます。
ただ、302リダイレクトを長期間設定していると、Googleが永続的な転送と判断して301リダイレクトと同じ扱いを受けることがあります。具体的な期間は明言されていませんが、302リダイレクトは1週間~2週間程度に留めておいた方が良いでしょう。
Googleは「301でも302でもSEOに大きな影響はない。状況に合う方を利用してほしい」としています。
元のURLに戻らないのであれば301リダイレクト、戻る予定があるのなら302リダイレクトと適切に使い分けましょう。
リダイレクト設定の流れ

リダイレクト設定をするには、まず新旧URLをリストアップし、リダイレクト方法を選定。テスト環境でリダイレクト設定をしたあとに本番環境へ移行します。ここではリダイレクト設定の流れをご紹介します。
1. 新旧URLのリストアップ
まずは新旧URLのリストアップを行いましょう。リストアップすることで、リダイレクトの抜け漏れを防ぎます。Googleもサイト移転の方法として、URLマッピングの準備を推奨しています。
リストアップでは、エクセルなどを用いて旧ページのURLと対応する新ページのURLを記載し、一覧を作成します。リニューアルに伴って、ページ内の画像や動画も移転する場合、画像や動画のURLも対応表が必要です。
大規模なサイトで手作業での抽出が困難な場合は、CMSで旧サイトのURLリストが取得できる場合があります。特に重要なページからリストを作成していきましょう。
基本的にはすべてのページにリダイレクト設定をすることが理想ですが、閲覧数の少ないページはユーザーニーズに応えられていない可能性が高いため、必ずしもリダイレクトをする必要はありません。リソースとのバランスが大切です。
なお、サイトリニューアル後に作られたページも、リストに含んでおきましょう。リダイレクトとは関係ありませんが、リストに加えておくことで全体像が把握しやすくなります。
2. リダイレクト方法の選定
次にリダイレクト方法を選定します。リダイレクト方法には、主に.htaccessファイルへの記述があります。
.htaccessファイルへの記述は、一般的なリダイレクトの方法です。.htaccessファイルとはサーバーを設定するファイルで、リダイレクトのコードを書き込むと転送が可能になります。
ただ、プログラミング言語を使用するため初心者にはハードルが高く、デフォルトの記述を削除したりコードを間違えたりすると、サイトが正常に機能しなくなる可能性があります。.htaccessファイルに記述を行う際は、先にバックアップをとっておきましょう。
この他にも、サーバーの管理画面やmeta refresh、Crypto、JavaScriptなどを利用する方法があります。ただ、CryptoとJavaScriptは、Googleが非推奨としているため、他に方法がない場合を除き、避けた方が良いでしょう。
3. テスト環境でリダイレクト設定
リダイレクト方法を決めたら、実際にリダイレクトを設定します。
ただ、最初から本番環境でリダイレクトを行うと、抜け漏れや記述の間違いなどがあった場合にトラブルになってしまいます。場合によってはサーバーが起動しないことも考えられるため、まずはテスト環境を用意し、テスト環境の中でリダイレクトを設定しましょう。
リダイレクト設定を行ったら、リダイレクトが正常に機能するか確認します。テスト環境で旧ページにアクセスし、問題なく新ページにアクセスできるかチェックしていきましょう。リダイレクトのページが多く、手作業でのチェックが面倒な場合は、リダイレクトチェッカーやGoogleのデベロッパーツールを利用する方法もあります。
4.本番環境に反映し改めて確認
テスト環境で問題なくリダイレクトができたら、本番環境に反映して再度確認します。確認の方法はテスト環境と同様です。
ページだけでなく、内部リンクや外部リンクなども適切に変更しましょう。同時にXMLサイトマップを用意することで、スムーズなインデックスも可能になります。
以前と変わらず、ユーザーにとってストレスのないサイトになっているか、確認しましょう。
リダイレクト設定の際の注意点

リダイレクトは正しく設定されていないと、ユーザーの混乱を招きます。ユーザーにこれまでと同じように快適に利用してもらうためには、いくつかの点に配慮しながらリダイレクトを進める必要があります。
ここではリダイレクト設定の注意点をご紹介します。URLのリストアップや、テスト環境・本番環境でリダイレクトを行う際には、後述する点に注意して設定やチェックを行いましょう。
リダイレクト先を正しく設定
リダイレクトで大切なことは「適切なリダイレクト先を確実に設定すること」です。先述しましたが、思っていたのと違うページに転送されたり、404エラーが大量に返ってきたりすると、ユーザービリティの低下を招きます。
新旧のURLをリストアップする際は、リダイレクト先が正しいか、内容が全く違うページにリダイレクトされていないかを確認し、実装でも再度チェックを行います。
Google Search Consoleを利用している場合は、ガイドラインに反しているリダイレクトに対して警告をしてくれる場合があります。その際は指示に従って修正を行うことで、正常なリダイレクトにできます。
なお、自社でリダイレクト先を正しく設定しても、マルウェアなどに感染した場合、意図せずフィッシングサイトなどにリダイレクトされる可能性もあります。基本的なセキュリティ対策はもちろん、定期的なチェックも忘れないようにしましょう。
URLは1対1でリダイレクトする
URLは1対1で、同じ内容のページにリダイレクトしましょう。旧ページと全く違う内容のページに誘導されるとユーザーが混乱してしまいます。
よくあるケースが、旧サイトのすべてのページを新サイトのトップページにリダイレクトするパターンです。
ユーザーは、自分の欲しい情報を求めて検索をしています。リダイレクトによって求める情報と違うページに転送されたらユーザーは不満に思いますし、ユーザーニーズを満たせないページは検索順位が下がる可能性もあります。検索順位が下がれば、アクセスやコンバージョンも減少してしまうでしょう。
1つのページにまとめてリダイレクトするのではなく、関連性の高いページに転送することが大切です。
リダイレクトループへの留意
リダイレクト設定の際は、リダイレクトループにならないよう注意が必要です。リダイレクトループとは、何らかの原因によって、リダイレクトが無限に繰り返される現象です。リダイレクトループに陥ると、ユーザーがページを閲覧できなくなり、サイトの信頼性が低下してしまいます。
リダイレクトループの要因はさまざまですが、一般的にはリダイレクト設定のミスが挙げられます。たとえばページAをページBに転送するようにしているのに、ページBがページAに転送する設定になっていると、無限にリダイレクトが繰り返されてしまいます。.htaccessファイルを確認するなどして、正しく設定されているかチェックしましょう。
設定が間違っていない場合は、キャッシュなどに問題がある可能性があります。キャッシュを削除するなど検証したりして原因を探りましょう。
リダイレクトループは、テスト環境で見つけておくことが重要です。テスト環境で修正しておくことで、本番環境での問題を減らせるでしょう。
リダイレクトチェーンへの留意
リダイレクト設定ではリダイレクトチェーンにも注意しましょう。リダイレクトチェーンとは、複数のリダイレクトが連続する現象です。たとえば、ページAからページBに転送したら、ページBにページCへのリダイレクトが設定されているといった状態です。
リダイレクトループと違い最終的にページの表示はされますが、表示速度の低下やクローリングしにくくなるなど、SEOに悪影響を及ぼす可能性があります。
リダイレクトチェーンを解消するには、不要なリダイレクトを削除します。先述した例であれば、ページAから直接ページCにリダイレクトするようにしましょう。シンプルな構造にすることでクローリングもしやすくなり、表示速度も速くなるでしょう。
Googleもリダイレクトチェーンを避けることを推奨しており、直接リダイレクトができない場合はチェーン内のリダイレクト数を5個未満(理想は3個未満)に抑えることとしています。
リダイレクト設定時のよくある疑問

リダイレクトを初めて行う場合は、さまざまな疑問があると思います。特に設定期間やチェック方法などは疑問に思う方も多いでしょう。ここでは、リダイレクト設定時のよくある疑問にお答えします。
リダイレクトの期間設定はどのくらい?
301リダイレクトの期間設定は一般的に1年以上とされており、Googleも1年以上を推奨しています。
Googleのクローラーは数回かけてサイト内をクローリングし、リダイレクトされたサイトが旧サイトから引き継がれたものだと認識します。クローリングがいつ完了するかは明確になっていませんが、大規模サイトでも1年程度あれば、すべてのページのクローリングが完了し「移転したサイトだ」と認識されるようです。そのため、最低でも1年はリダイレクトを設定しておきましょう。
ただ、Googleは「ユーザーの観点から、リダイレクトを無期限に保持することを検討してください」ともしています。これは旧URLをユーザーが訪れる可能性がある場合、リダイレクトを解除するとユーザーがページを閲覧できなくなるためです。リダイレクトの解除は、旧ページにユーザーが訪れなくなるまで待ちましょう。(参照:サイト・ホームページ移行について | Google 検索セントラル)
正しくリダイレクトが出来ているか確認するには?
正しくリダイレクトできているか確認するには、手動と自動の2つ方法があります。
手動は実際に旧ページにアクセスし、新ページに転送されるか、ひとつひとつ確認していく方法です。時間はかかりますがコストをかけずにできるため、ページ数の少ないサイトに向いています。
一方、ページ数が膨大なサイトを手動で確認するのは困難です。大規模サイトの場合は、先述したようにリダイレクトチェッカーやGoogleのデベロッパーツールなどを利用すると良いでしょう。
またこれまでご紹介してきたように、リダイレクトはSEOにも影響します。もしSEOの観点で不安がある場合は、SEOに詳しい制作会社などに相談することもひとつの方法です。
サイトリニューアルでアクセスを落とさないために

繰り返しになりますが、サイトリニューアルでのリダイレクトはSEOに大きく影響します。正しくリダイレクトを行わないと、アクセスやコンバージョンが減少する可能性があります。そのためデザインや機能だけでなく、SEOを意識したサイトリニューアルが重要です。不安があれば、制作会社に相談するのも良いでしょう。
ただし、制作会社にも得手不得手があり、SEOを意識したサイトリニューアルに対応してもらえない場合もあります。
株式会社シフトは、サイト制作からサイト構築後の運用まで一貫して相談できる制作会社です。SEOに配慮したサイト制作はもちろん、広告を使った集客やサイトリニューアル前のリダイレクトに関するご相談も受け付けています。
「サイトをリニューアルしたいけどSEOの評価を引き継げるか不安」「既存サイトのデータ移行はできるの?」といった悩みを抱えている方は、まずはこちらからご相談ください。
⇒サイトリニューアルについて相談する
まとめ
サイトリニューアルでURLやドメインが変更になった場合は、リダイレクトが必須です。正しく設定ができないと、リニューアルしてもアクセスやコンバージョンが増えないどころか、減少することも考えられます。ご紹介した点に注意しながら、確実にリダイレクト設定を行いましょう。