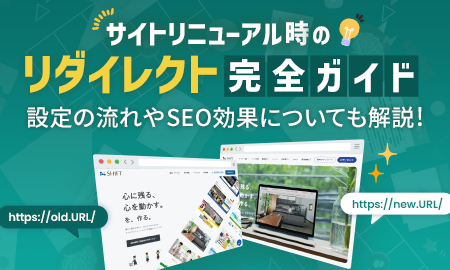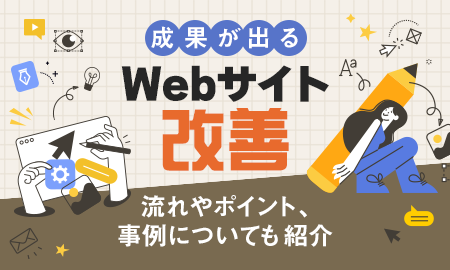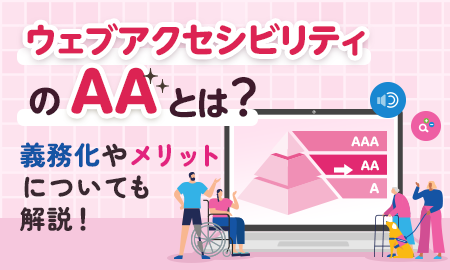ホームページの保守って必要?対応すべき内容や費用相場をご紹介!

ホームページを運用する上で「保守」は非常に大切です。保守はいわばホームページ運用の土台であり、保守がしっかりされていないと効果的な運用もできません。場合によっては、閲覧ができない、ユーザーがサイバー攻撃の被害に遭うなどのリスクもあります。
しかし、保守と言われても具体的に何をすべきかわからないという方もいると思います。本記事では、ホームページにおける保守の必要性や対応すべき作業などをご紹介します。最後まで読んでいただくことで、保守にかかる費用も理解できます。
ホームページの制作・リニューアルを考えている方の中には、CMSの導入を考えている方や現在使用されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
CMSのセキュリティリスクや対策方法、セキュリティに配慮したCMSの選び方などをご紹介した記事もございますので、ぜひご覧ください。
4社に1社が未対応?CMSに潜むセキュリティリスク、その危険性と対策について解説します
目次
ホームページの保守とは?

ホームページの保守とは、ホームページを安全に利用・運用できる状態を保つことです。
ホームページは常にトラブルのリスクに晒されています。サーバートラブルやサイバー攻撃などの外部要因はもちろん、設定ミスや更新忘れなど、内部のミスが原因で起こるトラブルもあります。
こうしたトラブルからホームページを守り、利用・運用を快適に行えるようにすることが保守の目的です。サーバーやドメインの管理、セキュリティ対策といった普段の備えのほか、トラブル発生時の対応も保守に含まれます。
なお、保守と似たものに「更新」と「運用」があります。更新はホームページの状態を最新に保つことであり、最新情報の発信や古い情報の削除を行うことです。運用はホームページの目的を達成するための施策を指し、SEO対策やアクセス解析、新しいコンテンツの追加などが主な内容です。
ホームページ保守の必要性
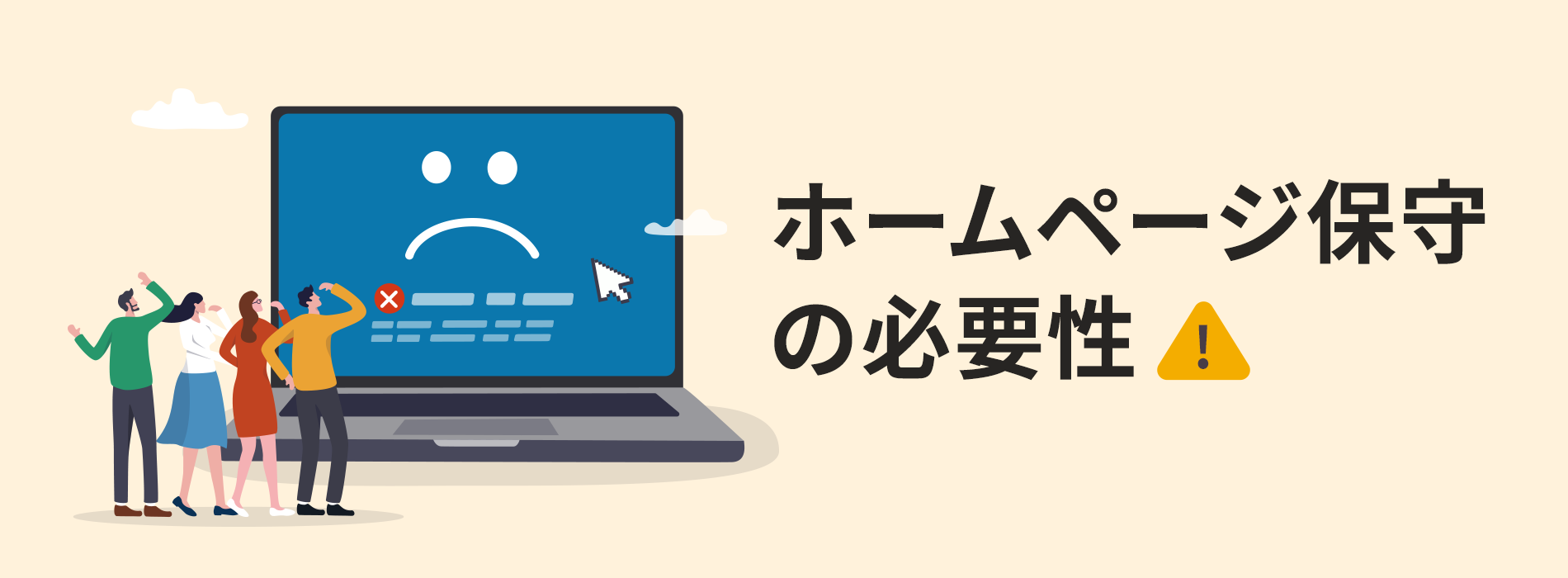
ホームページの保守は非常に重要です。なぜなら、保守は更新や運用の土台となる部分であり、適切にされていないと更新や運用がスムーズにできなくなる可能性があるためです。
たとえば、サーバーやドメインには有効期限が設定されており、利用し続けるには有効期限が切れる前に更新を行う必要があります。更新の手続きを忘れてしまうとホームページが閲覧できなくなり、その間はホームページでの営業が不可能になるでしょう。当然、更新や運用もできなくなります。
また、保守を怠ると余計なコストがかかります。株式会社サービシンクが行った「Webサイトやシステムの保守運用に関する実態調査」では「保守管理を怠ったために問題が発生したことがある」と回答した企業が67.3%。
そのうち、保守管理で発生した問題に対応するためにかかった費用や皺寄せとして、52.4%が「復旧対応にかかる費用」と答えています。また50.0%が「本来の業務時間が奪われる」、31.0%が「予算組みの変更と調整」と回答しており、本来必要なかったはずの業務や対応に時間を取られることも、営業活動の妨げとなるようです。(出典:Webサイトやシステムの保守運用に関する実態調査|株式会社サービシンク)
加えて、サイバー攻撃の被害にも遭いやすくなります。個人情報漏えいなどの問題が起これば、損害賠償だけでなく、信用低下といった社会的制裁も受ける可能性があります。リスクを防ぎ、更新や運用を続けるため、ホームページの保守はしっかり行いましょう。
ホームページの保守で対応すること
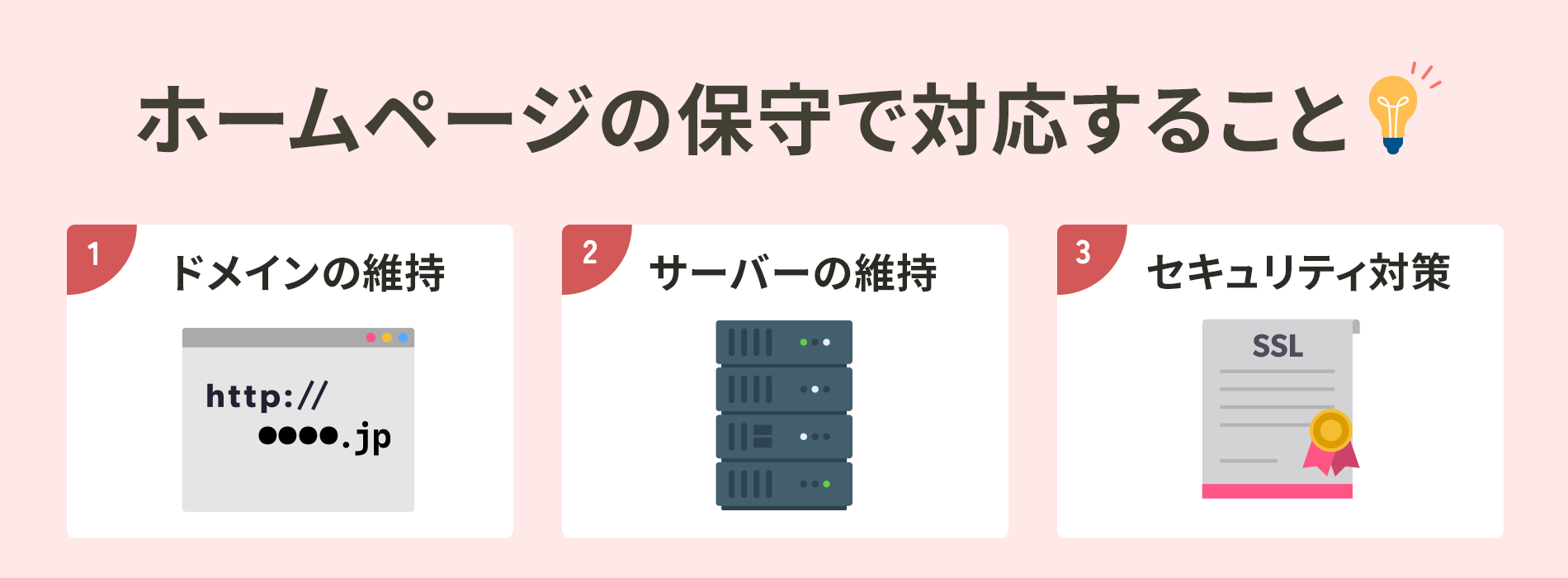
ホームページの保守で対応することは、ドメインとサーバーの維持やセキュリティ対策です。現在ホームページを運営している企業はもちろんですが、新規制作やリニューアルの際にも対応が必要なため、きちんと対応されているか確認しましょう。
ドメインの維持
ホームページの保守では、ドメインの維持が重要です。ドメインとは、ホームページの場所を表したもので「インターネット上の住所」とも呼ばれます。URLやメールアドレスなどに利用されており、企業では独自の文字列を使用した「独自ドメイン」が使われていることがほとんどです。
ドメインの維持が重要な理由は、ホームページの適切な運用にドメインの維持が必須となるためです。先述したようにドメインには有効期限が設けられており、期限を過ぎると失効して、ホームページの閲覧ができなくなります。
さらに失効から一定期間を過ぎると、これまで使用していたドメインを別のユーザーが取得することも可能です。もし別のユーザーが取得すれば、ドメインを元に戻すことはできず、新しいドメインを取得するしかありません。ドメインが新しくなれば、URLが変更になったことをユーザーに知らせたり、名刺やパンフレットの修正をしたりといった作業が必要となり、余計なコストがかかるでしょう。
また失効したドメインを他者に悪用されて、ブランドイメージを落とされる可能性もあります。近年では悪用を防ぐために、自社に関連する文字列のドメインを複数取得する、不要になったドメインでもしばらくは解約しないなどの対策を採っている企業もあるようです。
ホームページを適切に運用するためには、ドメインの管理をしっかり行うことが大切です。ドメインの管理では定期的な保守などは必要なく、基本年1回の更新費用を支払うだけです。ただ、支払いを忘れる可能性を考慮したリスクヘッジが必要です。管理は複数人で行う、ドメイン管理を委託するなどの方法で、確実に更新できるようにしましょう。
サーバーの維持
サーバーの維持もホームページの保守では重要です。サーバーはホームページのコンテンツを保管しておく場所であり、インターネット上の土地のようなものです。サーバーにはWebサーバーやデータベースサーバー、メールサーバーなど複数の種類があり、役割によってサーバーが分かれていることもあります。特に膨大な情報を扱うシステムではサーバーは用途で分かれていることが一般的です。
サーバーもドメインと同じように有効期限があり、有効期限を過ぎるとホームページが閲覧できなくなります。場合によってはサーバー上にあったホームページのデータが消えてしまい、復元できなくなる可能性もあります。メールやシステムも利用できなくなり、業務を止めざるを得なくなるでしょう。
一般的に企業はレンタルサーバーを利用していることが多く、定期的なメンテナンスなどを自社側で行う必要はありません。ただドメイン同様、有効期限内に更新費用を支払う必要があります。
なお、サーバーは容量に対して負荷が大きいとダウンしやすくなります。アクセス数や機能などを考慮してホームページに適切なサーバーを選ぶことが重要です。
セキュリティ対策
ホームページではしっかりしたセキュリティ対策を行いましょう。
ホームページには必ず「脆弱性」があります。脆弱性とは設計やプログラムのミスでできるセキュリティ上の穴で「セキュリティホール」とも呼ばれます。悪意のあるユーザーは脆弱性を狙って攻撃を仕掛けてくるため、ホームページの保守では脆弱性を極力減らすことが重要です。
警察庁の「令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、脆弱性探索を目的とした不審なアクセスは年々増加しており、令和6年上半期は9825万件にも及んでいます。
ほとんどが海外からのアクセスです。また攻撃者とランサムウェアの開発者が異なっている、AIを使って悪意のあるプログラムを作成した人物が逮捕されるなど、サイバー攻撃も巧妙で高度なものに変化しています。(出典:令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について|警察庁 サイバー警察局)
ホームページの公開は世界中からのアクセスが可能になりますが、その分不正アクセスの発生率も高くなります。OSやミドルウェア、アプリなどのアップデート、ファイアウォールやWAFの適切な設定などで、不正アクセスから情報を守りましょう。
セキュリティ対策について、くわしく知りたい方は下記よりご覧ください。
ホームページに必要なセキュリティ対策とは?
SSLサーバー証明書
セキュリティ対策として備えておきたいものが「SSLサーバー証明書」です。SSLとは送受信するデータを暗号化するプロトコルで、SSL証明書はプロトコルを実行するために必要な証明書です。データを暗号化することで悪意のある第三者が閲覧できないようにしています。SSL化されているホームページは、URLの頭が「http:」から「https:」になります。
SSLサーバー証明書がなくても、ホームページの閲覧が不可能になることはありません。ただ近年ではユーザーのセキュリティ意識の高まりによって、SSL化されていないホームページは敬遠される傾向にあります。Googleも2014年に「ランキングシグナルとしてHTTPSを使用する」と発表しており、SSL化された安全性の高いホームページがSEOで評価される傾向にあります。
王道DXの「世界主要企業サイト/国内主要企業サイト 常時SSL化対応調査」では、国内主要企業の99.6%がホームページをSSL化しているという結果が出ており、ホームページの保守においてSSL化は当たり前の対応となっています。ホームページの制作やリニューアルにおいては、SSLサーバー証明書を導入しましょう。(出典:世界主要企業サイト/国内主要企業サイト 常時SSL化対応調査|王道DX)
SSLサーバー証明書も、ドメインやサーバー同様、有効期限があります。セキュリティの観点から自動更新は行われないため、都度更新の手続きや費用が必要です。
なお2025年2月現在、SSLサーバー証明書の最長有効期間は398日ですが、セキュリティリスクを鑑みて、有効期限を短縮する動きが出ています。草案では2026年3月から徐々に最長有効期間を短くしていき、2028年3月には47日にするとしています。
最新バージョンへの対応
ホームページ保守のセキュリティ対策としては、最新バージョンへの対応も必要です。CMSやブラウザ、端末などを最新に保つことで、安全性を高められます。
先述したように、サイバー攻撃ではシステムやサーバーの脆弱性を突いて攻撃を仕掛ける場合が多いです。そのためCMSやアプリなどは、脆弱性を修正したプログラムを新しく配布してセキュリティホールを埋めていきます。
もし古いバージョンを利用していると、脆弱性を突かれてサイバー攻撃の被害に遭うかもしれません。近年では脆弱性を公表してから対応プログラムを配布する前に攻撃をしかける「ゼロデイ攻撃」もあり、脆弱性が見つかってから最新バージョンに更新する間も注意が必要です。
自動でアップデートされる場合でも、最新のバージョンに更新されているか確認しましょう。ブラウザや端末が新しくなった場合には、最新バージョンで問題なく閲覧・動作できるかも確認が必要です。
ホームページ保守管理費用の相場
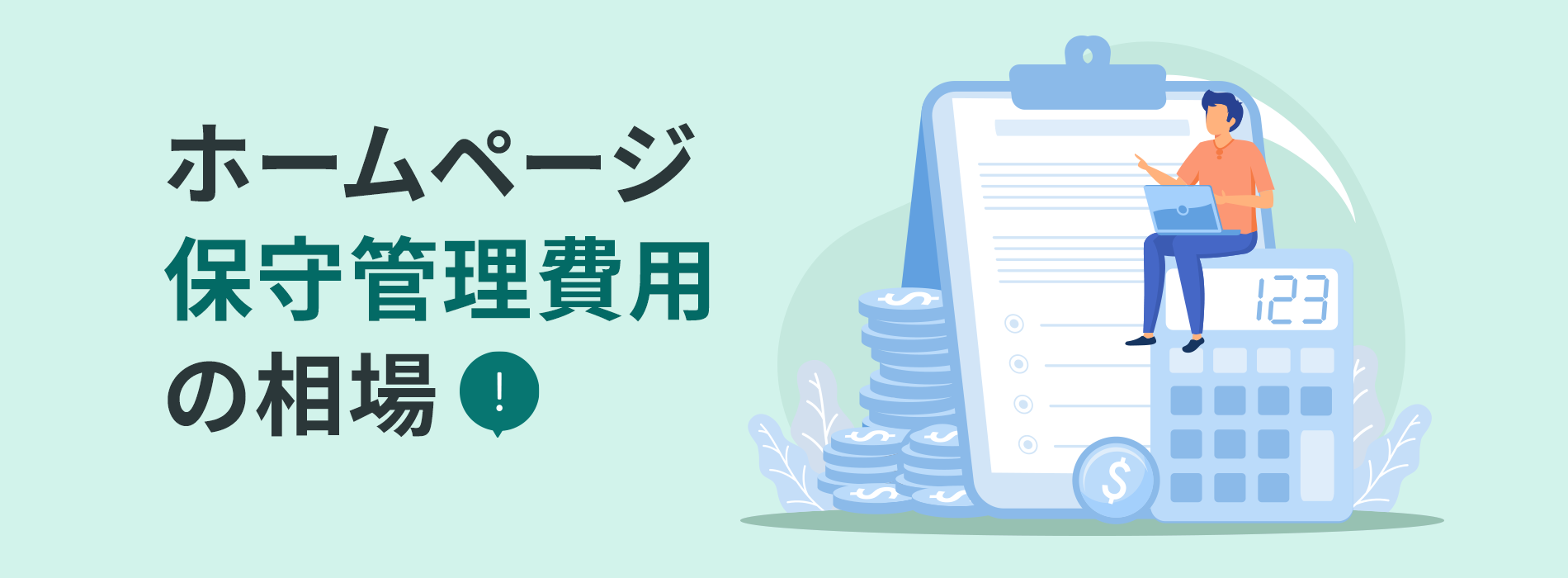
ドメインやサーバーの維持、セキュリティ対策など、ホームページの保守にはある程度の費用が必要です。安全性の高い保守管理を行うほど、かかる費用も多くなります。ここではホームページの保守管理内容を金額別に分けてご紹介します。
月額1万円以下
月額1万円以下でも、ドメインやサーバーの維持、SSLサーバー証明書の導入は可能です。こだわりがなければ、ドメインとSSLサーバー証明書は無料で利用できるものもあります。
ただし、ホームページの保守としては必要最低限です。保守管理を外注するには足りないため、サーバーやドメイン、SSLサーバー証明書の管理は自社で行います。そのため、自社内で管理を行うための知識やリソースが必要です。コンテンツの修正や運用なども基本的には自社で行うことになります。
特にネックになることが、トラブル対応です。サポートを受けることが難しいため、万一トラブルが起こった場合は自社で対応する必要があります。トラブル対応が本来の業務の妨げとなる場合もあるでしょう。
また自社管理によってセキュリティが甘くなれば、サイバー攻撃などで情報が流出して、法的・社会的な責任を問われる可能性もあります。費用を抑えられることは良いですが、知識やリソースが不足していればリスクが大きいことも考慮しましょう。
月額1万円~3万円
月額1万円~3万円の場合、サーバーやドメイン、SSLサーバー証明書の維持に加えて、コンテンツの更新や修正作業、トラブル対応なども依頼できます。企業ホームページの保守管理としては最も一般的な価格帯と内容で、中規模程度の制作会社に依頼可能です。コーポレートサイトなど、コンテンツの更新が月に数回程度のホームページならこの価格帯で十分でしょう。
一方、ニュースサイトなど毎日のように更新が必要なホームページの場合、更新を依頼し続けることが難しいため、更新は自社で行うなどの対応が必要です。
月に数回程度の更新が含まれていると記載しましたが、大規模なリニューアルやCMSの完全アップデートなど作業に時間がかかるものに関しては、別途料金を請求される場合が多いです。制作会社によって対応範囲が変わるため、依頼前に確認しましょう。
月額3万円~10万円
3万円~10万円の保守管理費用がある場合、一般的な保守管理に加え、CMSの管理やアクセス解析レポートの提出なども依頼できます。中小規模や大手の制作会社にも依頼ができる価格帯で、ホームページの包括的な保守が可能です。中には自社独自のサービスをプラスで提供してくれるところもあります。
アクセス解析レポートはあくまで参考程度で、集客のためのアドバイスをもらうなら、最低でも5万円は必要です。社内にマーケターがいる場合、レポート作成だけをお願いして、分析や施策の企画などは社内で行うという利用方法もあります。
ただし簡単なアドバイスを受けることはできても、本格的な集客を依頼することは難しいでしょう。先述したように、制作会社によって対応できる範囲が違うため、お互いの対応範囲を確認することが大切です。
10万円以上
保守管理費用が10万円以上になると、一般的な保守に加えて、コンテンツの更新・修正、トラブル対応、CMSの管理のほか、アクセス解析レポートの提出や集客支援なども依頼できます。SEO対策を含めたコンサルティングも可能で、場合によっては施策の実行まで任せられることもあります。発注先は主に大手の制作会社です。
10万円以上の保守管理費を用意できる場合は、保守管理とマーケティングをそれぞれ専門性の高い別会社に依頼するケースもあります。制作からマーケティングまで行ってくれる制作会社もありますが、コンサルティングに関する専門知識や実績があるかを見極めることが大切です。
自社内で運用を行うリソースや知見がない場合や、初めてのWebマーケティングでやり方がわからないという場合は保守管理費用を多めに確保して外注するのが良いでしょう。
| 相場(月額) | 保守管理内容 | 依頼先 |
| 1万円以下 | サーバー維持/ドメイン維持/SSLサーバー証明書維持 | 自社管理 |
| 1万円~3万円以下 | サーバー維持/ドメイン維持/SSLサーバー証明書維持/コンテンツ更新・修正(月数回)/トラブル対応 | 中規模程度の制作会社 |
| 3万円~10万円 | サーバー維持/ドメイン維持/SSLサーバー証明書維持/コンテンツ更新・修正/トラブル対応/CMS管理/アクセス解析レポート作成 |
中規模程度の制作会社 |
| 10万円以上 | サーバー維持/ドメイン維持/SSLサーバー証明書維持/コンテンツ更新・修正/トラブル対応/CMS管理/アクセス解析レポート作成/SEO対策などの集客支援・コンサルティング |
大手制作会社 |
保守管理費用のほか、ホームページの制作費用にかかる相場や制作方法、事例などをご紹介している記事もありますので、ご参考にしてみてください。
会社ホームページの作成方法や手順、費用などを解説
ホームページの保守で注意したいこと
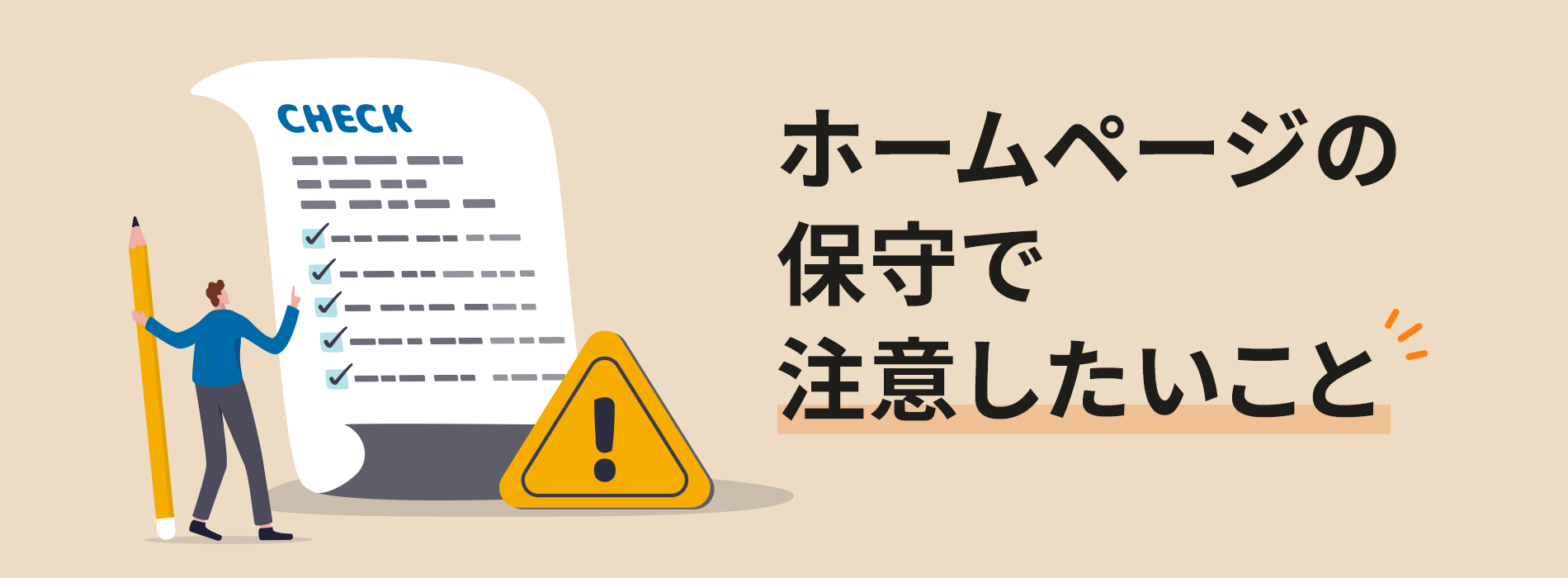
ホームページの保守では、サーバーやドメインの管理、セキュリティ対策などを行っていきますが、注意したい点がいくつかあります。これらを意識した保守管理を行うことで、よりスムーズにホームページの保守が行えます。ここからは、ホームページの保守で注意したい点を、自社管理と外注に分けてご紹介します。
自社で注意すること
自社で注意すべきことは、自社管理部分の対策をしっかり行うことです。特にサーバーとドメインに関しては、所有者を自社にすることが基本のため、サーバーのセキュリティやデータについては自社側での対策が必要です。
サーバーとドメインは自社で持つ
サーバーとドメインは、自社で契約しましょう。仮に制作から運用まで制作会社に一任するとしても、サーバーとドメインの所有者は自社にしておくことをおすすめします。なぜなら自社保有にすることで、調整が迅速かつ的確に行えるためです。
たとえば、サーバーに障害が発生した場合も、自社保有のサーバーであれば、原因を突き止めて適切な対応ができます。容量の追加やコスト削減のための移管なども自社判断で可能です。
もしサーバーやドメインも制作会社に依存してしまうと、自社内でコントロールができません。ドメインやサーバーの移管をしたいと思っても、制作会社に拒否されれば移管は不可能です。もしサービスを停止されれば、ホームページが閲覧できなくなるだけでなく、ホームページに保存されていたデータも消えてしまいます。
またドメインを処分された場合、新しくドメインを取得し直す必要がありますが、先述したように処分されたものと同じドメインは一定期間が経過しないと取得できません。加えて、ドメインパワーもリセットされるため、SEO対策を最初からやり直す必要があります。
複数のバックアップを取っておく
バックアップは複数取っておくようにしましょう。バックアップはセキュリティ対策の基本ですが、複数のバックアップがあることで、安全性を高められます。
バックアップは「3-2-1ルール」に従うと良いでしょう。3-2-1ルールとは、バックアップを取るときの効果的な方法で「3つのデータを、2つの異なるメディアに保存し、1つは遠隔地に」というルールです。3つのデータが同時に破損・消失するのは稀ですし、異なるメディアに保存することで、1つのメディアが破損しても他のメディアに保管されたデータでカバーできます。また1つのデータを遠隔地で保管しておけば、災害などで近くのデータセンターが機能しなくなった場合でも、遠隔地のバックアップが利用できるでしょう。
警察庁の「令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、ランサムウェアの被害に遭った企業の内、データを復元できなかった企業が約7割。復元できなかった理由の7割はバックアップも暗号化されたためでした。こうした事態も複数の箇所にバックアップを取ることで、防げる可能性が高まります。(出典:令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について|警察庁サイバー警察局)
なお、近年のバックアップはツールなどで自動化できます。ただ、自動バックアップだけでなく手動でも行って、きちんとバックアップが取れているか確認することも重要です。
不正アクセスに注意する
不正アクセスにも十分な注意が必要です。ホームページは公開された瞬間からサイバー攻撃のリスクに晒されます。先述したように、脆弱性探索を目的とした不審なアクセスは年々増えているため、セキュリティ対策を行って不正アクセスを防ぐことが大切です。
特に「WordPress」を利用している場合は注意が必要です。気軽に利用できることから大きなシェアを誇るCMSですが、オープンソースであるためソースコードが公開されており、ソースコードを解析して脆弱性を突くユーザーがいます。加えて個人がテーマやプラグインなどを提供していることから、プラグインやテーマのセキュリティの甘さを利用する場合もあるようです。
不正アクセスされると、乗っ取りや詐欺サイトへの誘導、マルウェアによる情報漏えいが起こる可能性があります。こうした事態になれば信用性が低下して、企業の営業活動に影響を及ぼします。費用をかけて保守を行うことは、情報を守り、ユーザーを守り、結果自社を守ることにつながります。
制作会社に依頼する際に注意すること
ホームページの保守を制作会社に依頼する場合は、お互いの作業範囲や相性などを確認することが重要です。しっかりコミュニケーションをとって、制作会社の実力を見極め、齟齬のない依頼を行いましょう。
作業範囲・費用を明確にする
制作会社に依頼する際は、お互いの作業範囲と費用を明確にしましょう。
保守管理の費用や内容は、制作会社によって違います。費用内に含まれている作業を明確にしておかないと、自社で対応する作業もわからず、のちのちトラブルになる可能性があります。認識の齟齬がないように、書面などで範囲を明確にしておくことが重要です。
もし自社側で対応する作業があれば、制作会社に伝えましょう。たとえば、コンテンツ更新は自社側で行い、CMSの管理やトラブル対応は外注するなどの方法も可能です。
可能であれば、保守管理には費用をかけることをおすすめします。費用をかければ、十分な保守管理を行えます。
自社に合った制作会社へ依頼する
制作会社に保守を外注する際は、自社に合った制作会社に依頼しましょう。制作会社の提供するサービスが自社のニーズと合致するかはもちろん、担当者との相性やコミュニケーション能力、実績などを加味した上で制作会社を選ぶことが大切です。
依頼の際は複数の制作会社から見積もりを取りましょう。保守管理の内容やサポート、オプションなどを比較して、自社の費用感と合っている制作会社を選ぶと良いでしょう。
制作会社の選定ポイントや選定方法などを記載した記事もありますので、ぜひ下記よりご覧ください。
失敗しない!ホームページ制作会社の選び方
ホームページは保守だけでなく“運用”も大切!

ホームページの維持や安全性を高めるために、保守をしっかり準備することが大切です。
その次に行うべきことは、ホームページを運用していくことです。ホームページの基盤をしっかりと固めたうえで、自社のターゲット層から求められているニーズを把握し、運用していくことで、認知拡大や集客の向上などホームページを制作した本来の目的を達成することができます。
ホームページの運用を制作会社などに外注することも可能ですが、「ホームページの内容更新をすぐに反映させたい」「コストや手間をかけずに更新したい」などお考えの方は、CMSでの運用も選択肢の一つになります。
株式会社シフトのパッケージCMS「SITEMANAGE」では、直感的な操作性で誰でも簡単に操作することができるため、ホームページの更新を自分たちですぐに反映することができます。また、自社の運用方法に合わせて機能をカスタマイズ・開発を行うことが可能です。
CMSでのホームページ制作・リニューアルについてご相談したい方は下記よりお気軽にご相談ください。
ホームページ制作・リニューアルについて相談する
まとめ
ホームページの保守を怠ると、ホームページの閲覧ができない、サイバー攻撃の被害に遭うなどのトラブルが考えられます。保守を効果的に行うにはそれなりの費用が必要ですが、安全にホームページを閲覧・運用していくためには必要なことです。先述した注意点などに留意しながら、ホームページを維持していきましょう。